Contents
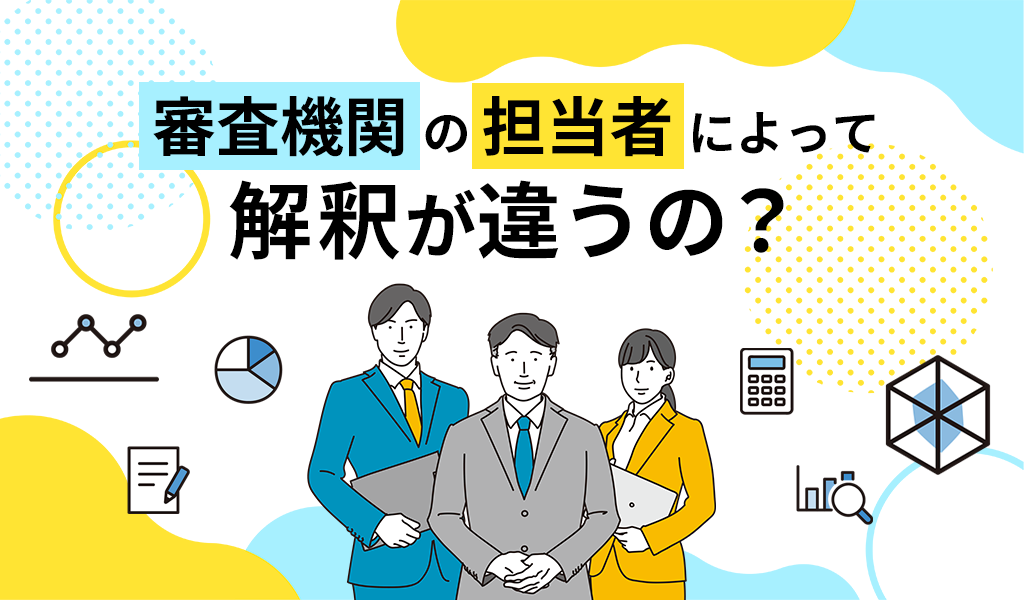
建築業界や不動産関連の業務に携わっていると、さまざまな「審査機関」と関わることになります。たとえば、建築確認、長期優良住宅の認定、省エネ性能の評価、補助金の適用判断など、あらゆる場面で審査という壁を乗り越えなければなりません。
ところが、こんな経験をしたことはありませんか?
・前回と同じ資料で出したのに、今回は違う指摘が返ってきた
・A社では何も言われなかったのに、B社では細かく修正を求められた
・担当者が変わった途端、やたら厳しくなった
こうした体験から、「審査って、担当者によって解釈が違うのでは?」と疑問や不満を感じる人も少なくありません。本記事では、そういった疑問に答える形で、審査機関の仕組みや役割、担当者ごとの違いが起こる理由について詳しく解説します。
審査機関とは
「審査機関・評価機関」とは、法律や制度、行政指針などに基づいて、建築物や住宅の設計・仕様・性能が適正であるかどうかを確認・認証する第三者機関のことを指します。
審査機関は行政機関とは異なり、民間の法人であることが多く、公平性・中立性を保ちながら、専門知識を持った技術者が図面や資料をチェックしています。建築士や構造設計の専門家、省エネ計算に精通した技術者などが在籍し、それぞれの基準に照らして審査を行います。
審査の対象となるのは建築確認や住宅性能評価だけにとどまらず、長期優良住宅、低炭素建築物、ZEH、BELS、各種補助金の交付要件の確認など、年々その役割は広がっています。
コメント