Contents
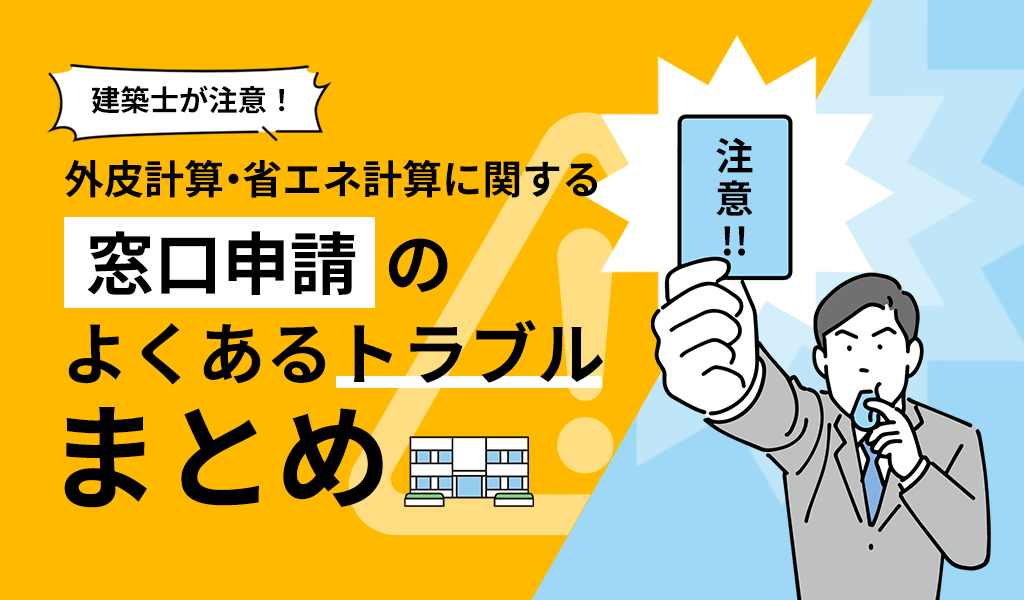
2025年4月以降は、設計士が新築住宅やリフォームの設計を行う際、省エネ適合性判定が必要となるため、省エネ計算を行い、これらの計算結果を審査機関に申請する必要があります。
しかしながら、手続きがスムーズに進まないケースも考えられます。本記事では、建築士が省エネ計算において直面しがちなトラブルやその対処法を詳しく解説します。
計算書類の不備
外皮計算・省エネ計算の書類は、非常に詳細な情報が求められます。特に多いトラブルの一つが、提出書類の不備です。よくある例として以下のようなものがあります。
1,入力データの誤り
建物の仕様に合わせた断熱材の厚さや性能値(熱貫流率など)を正確に反映していないことが指摘されることがあります。例えば、断熱材の種類や厚さが計算書と実際の設計図面で異なると、修正を求められることがあります。2,計算ミス
計算ソフトを使用しても、人為的な入力ミスが原因で結果が誤っているケースがあります。特に、窓の面積や熱貫流率(U値)の計算に誤差が生じやすいです。3,添付資料不足
断熱材や窓のカタログ、仕様書などが不足している場合、追加提出を求められることがあります。
対策
提出前にダブルチェックを行うことが重要です。特に複数人での確認作業を行うと、見落としを防ぐことができます。また、専門ソフトを使用して計算した場合でも、最終的な確認を怠らないようにしましょう。
コメント