Contents
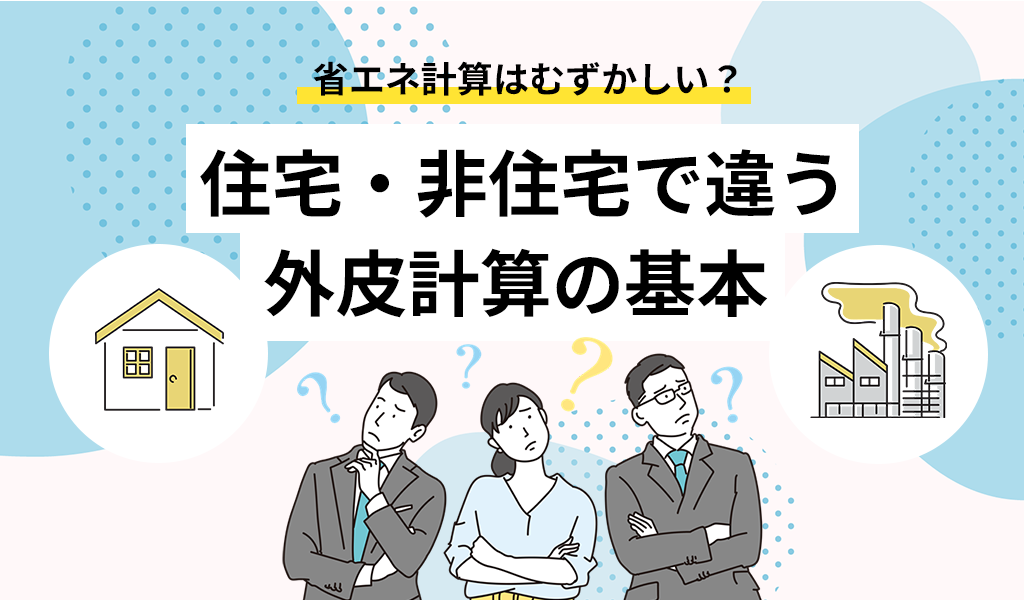
<この記事は約3分で読めます>
いまさらだけど省エネ計算とは?
建築物省エネ法の概要
建物の省エネルギー性能を評価するためには、国が定める基準に基づいた計算が必要です。これを「省エネ計算」と呼びます。日本では「建築物省エネ法(正式名称:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)」がその根拠法となっており、新築・増改築において一定規模以上の建物には適合義務や届出義務が課せられています。
省エネ計算は単に「電気代を下げるため」ではなく、国全体で温室効果ガスを削減し、持続可能な社会を実現するための重要な取り組みです。そのため、設計段階から建築士や設備設計者が協力して正確な計算を行うことが求められています。
住宅・非住宅での省エネ基準の違い
省エネ計算の大きな特徴は「住宅」と「非住宅」で評価方法が異なる点です。
住宅の場合は、断熱性能を示す外皮性能(UA値・ηA値)と、暖冷房・給湯・照明・換気といった一次エネルギー消費量の両面で基準を満たす必要があります。つまり、家そのものの「熱の逃げやすさ」と、生活に必要な設備エネルギーの効率性を同時にチェックするわけです。
一方、非住宅建築物(オフィスや学校など)では、建物用途や設備容量が多様であるため、主に一次エネルギー消費量を基準に評価します。外皮性能も計算対象にはなりますが、住宅に比べると相対的に比重は小さく、設備面の効率が大きなポイントとなります。
コメント